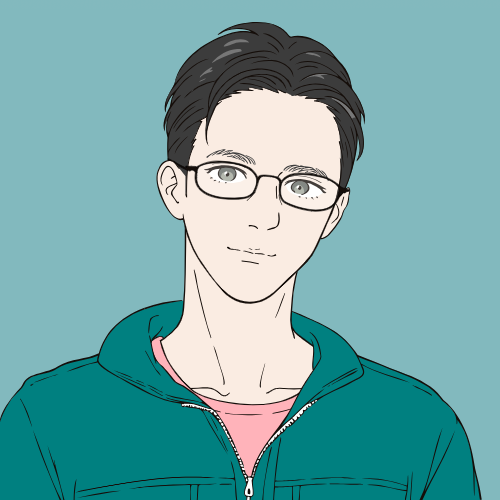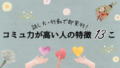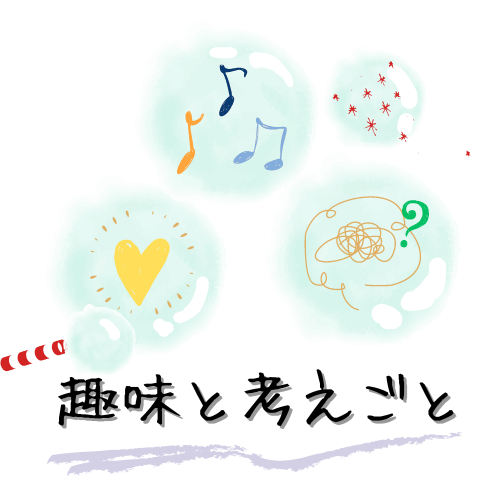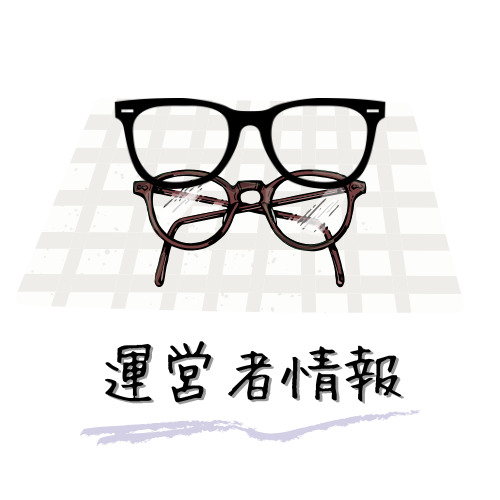本記事では「高専のレポートの書き方」を解説しています。
「レポート作成の詳細を知りたい」「中身を充実させたい!」とお考えではありませんか?
とくにレポート初心者は、どこから手をつけるべきか悩んでしまいますよね…。
本記事では「高専でのレポートの書き方」以外にも「構成の作り方」「考察ポイント」まで、高専OBが解説しています。
高評価必至のレポートが書けるようになりますよ!
- レポートの書き方が分からない人
- 実験中の着眼点を知りたい人
- 高評価されるポイントを知りたい人
「レポートの評価次第で、修了後の進学も考えたい!」という人は以下の記事もどうぞ!
さっそく「高専のレポートの書き方」をみていきましょう。
┄MENU┄
なぜ?高専でレポートを書く理由

高専でレポートを作成する最大の理由は、自分の実験内容を他者に理解してもらうためです。
自ら行った実験を的確に記述する練習としてレポートを作成します。
さらに深堀しますと、本格的にレポート作成が始まるのは、3年生の実験~でしょうか。
はじめのうちは慣れない作業が多いため、時間に余裕をもってスタートするとよいでしょう。

ちなみに、機械・電気・化学分野は、実験内容や作業が多いためレポートに時間がかかります。
以上を簡単にまとめると、実験内容を的確かつ明確に他者へ提示するために、レポートの作成法を学習します。
レポートに役立つ!準備~実験で意識すること

以下からは、のちのレポート作成に役立つ観点をみてみましょう。
実験前の注目点
実験を始める前に、目的の把握・事前準備の2つは欠かせません。
一つずつ解説します。
①実験目的の理解
実験を行う目的や狙いを、正しく理解することが重要です。
なぜなら、のちのレポートにも記載する必要があり、完成度に直結するからです。
例えば「何を明らかにしようとしているか」や「どの理論を検証するか」など。
明確かつ具体的にすることで、おのずと結果の考察もスムーズになります。
そのため、レポートの評価を上げるためにも、実験目的・狙いをはっきりさせておくとよいでしょう。
②実験器具・安全対策の確認
使用する器具・機器の取り扱い方法を確認します。
実験中は、スピード勝負になることも。
器具の操作を間違えないよう、計測範囲や精度について把握しておく必要があります。
また、安全対策の徹底も必須です。
とくに、化学薬品の取り扱いがある実験や、高温・高圧の実験は思わぬ事故につながる可能性があります。
そのため、保護具(ゴーグル、手袋など)の装着・換気など安全対策を徹底しましょう。

実験器具・安全対策の記載もレポートには必須!
忘れずに書いておきましょう。
実験中の着眼点
レポートの核ともいえる実験。
作成に活かせるポイントを、時系列に合わせて解説します。
実験中:データ測定・記録
実験中に意識すべき要点は、おもに3つあります。
| 要点 | 詳細 |
| ①データの正確な記録 | 実験で得られた数値データを正確に記録。 |
| ②再現性の意識 | メモは、他者が再現しても同じ結果になるように考慮しながら。 |
| ③問題発生時の対応/記録 | 臨機応変に対応し、行ったことを記録。 機器・器具などの条件だったり温度・湿度などの環境だったり、実験の反応に応じて変化させることが大切。 また、想定外のことが起きた場合(データが大幅に異なる、装置の故障など)は、原因の模索&改善策を検討する。 |
以上のとおり、実験中は記録作業が必須です。
後々のレポート作成を考えて、事実をまとめておくことがポイントです。
終了後:データ分析
実験終了後、結果のまとめをします。
優れた考察につなげるため着目点は以下のとおり。
| ポイント | 詳細 |
| グラフや表に整理して可視化 | 取得したデータをグラフや表に整理することで、視覚的に傾向の把握が可能。 |
| 理論との比較 | 学んだ理論と、実験から得られた結果を比較しながら確認。 理論通りの結果が得られない場合、その理由を追求する。 |

データの整理には、Excelやスプレッドシートが大活躍でした!
高専のレポート まとめ方

完成度の高いレポートを作成するにはどうしたらよいのでしょう?
以下からは、高専のレポートの書き方を詳しく解説していきます。
レポートの基本構成
実験後の実験レポートは、通常以下の項目で構成されます。
| 必要な項目 | 詳細 |
| 表紙 | レポートのタイトル・日付・学籍番号・氏名を記載。 |
| 目的 | 「何を明らかにするために行ったのか」を簡潔に! |
| 原理・背景 | 問題点・背景の説明・使用する理論や公式について・関連する法則・工学的理論を示す。 実験の意義や結果の妥当性の理解を促しやすい。 |
| 手順 | 使用した器具・機器・実験手順をくわしく!再現性(他者が同様の実験を行っても同じ結果が出ること)が重要。 |
| 結果 | 実験から得られたデータを示す。数値データは、視覚的な傾向把握を促すために、表やグラフでの整理がおすすめ◎ |
| 考察 | 得られた考察・仮説の検証・誤差の要因を記述。ポイントは後述します。 |
| 結論 | 以上から何が述べられるか、その結論を簡潔にまとめる。成果・気づき・実験目的に対する結論を含めるとgood! |
| 参考文献 | 参照した教科書や論文などの出典を記載。 |
それぞれの内容を明確に記載することで、レポートがわかりやすくなります。
考察の記載ポイント
上記の基本構成の中でも、考察は最も難しい部分といえるのではないでしょうか。
なぜなら、自分の考えを言語化する必要があるからです。
目的と結果を照らし合わせながら、優れた考察力を発揮しなければいけません。
「どこに着目したらいいんだろう?」とお悩みの人は、まず以下の2点を考慮してみましょう。
| ポイント | 詳細 |
| 結果と理論の一致 | 実験結果と理論が一致しているかを確認。 一致している場合はその理由を、理論と異なる結果が出た場合は、要因を分析したうえで改善策までを提示。 |
| 誤差要因の分析 | 実験結果への影響が考えられる要因を考察。 測定誤差や実験条件の変動、器具の精度・分解能など。 |
高評価の高専レポートを書くには?
実験の評価は、レポートの完成度が最大のカギ。
質を上げて、高評価につなげるコツ・裏ワザを以下にまとめました。
| コツ・裏ワザ | 詳細 |
| 客観的な表現 | 事実を記述し、客観的視点から記述する。 |
| 簡潔かつ正確な表現 | 簡潔でわかりやすい文章に。 冗長表現や複雑な言い回しは避ける。 |
| 整ったレイアウト | 図表や見出しを活用し、読み手にわかりやすい表現に。 |
| 提出前の確認 | 誤字脱字や計算ミス、データの漏れがないか、提出前に確認を。 他者に頼み、客観的な視点からチェックしてもらうのもgood! |
| デジタルツールの活用 | Excelやグラフ作成ソフトなどを活用し、視覚に訴えるのもおすすめ。 |
| 過去レポートの活用 | 先輩方からの過去レポートを参考にするのも手。 参考ポイントは、実験背景や流れなど。 |

ちなみに「過去レポート」は参考までに!
結果や考察まで同じだと、パクリを疑われることもあるので注意!
高専のレポートの書き方 まとめ

本記事では「高専のレポートの書き方」を中心に解説してきました。
- レポート作成の理由は、自分の実験内容を他者に理解してもらうため
- 実験前の注意点は目的の把握・事前準備の2つ
- 考察ポイントは「結果と理論の一致」「誤差要因の分析」
- 過去のレポートを参考にするのも手
「レポートの書き方がわからない…」「評価されるレポートを仕上げたい」という人のお役に立てれば嬉しいです。
高専でのレポートは、目的と結果の差異を論理的に考え、問題解決能力を養うための重要な学習。
質の高さを追求することで、修了後の進路も変わる可能性があります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。